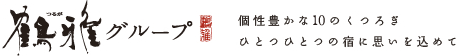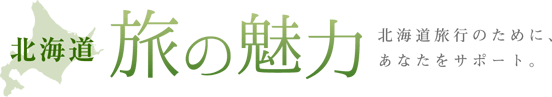それははるか昔。7世紀から9世紀の頃。アムール川下流域から流氷に乗って、このオホーツクへとたどり着いた民がいました。この民族は「オホーツク人」と呼ばれ、彼らが築いた「オホーツク文化」は未だ謎を残していますが、一方で多くのことも解明されてきました。東京大学の熊木俊朗准教授は、「ところ遺跡」を発掘・研究し「オホーツク人」の素顔を探求し続けている人です。
流氷が消えた春のオホーツク海は、豊饒をたっぷりと抱き、今日も静かに凪いでいます。「サロマ湖鶴雅リゾート」の前の道を渡り、坂道を少し登って行くと見えてくる赤い屋根。ここが、「東京大学大学院人文社会系研究科 附属北海文化研究 常呂実習施設」。熊木准教授が11年間を過ごしてきた研究の場です。同大学は50年に渡り、「ところ遺跡」を拠点に「北海道先住民」を研究してきました。
「オホーツク人はトドやアザラシを狩猟した海洋民族ですが、陸動物の狩猟にも長けていました。ヒグマは信仰のために、そしてテンやキツネの毛皮は大陸などとの交易に使っていたようです。男性の平均身長は160センチくらい。顔が大きく、鼻は低かった。大きな5角形、6角形の縦穴住居に数家族が住み、住居内にはヒグマの頭蓋を祀った骨塚が見られます。ヒグマ崇拝は、のちに出現するアイヌ社会の「クマ送り」儀礼に似ていますよね?」。熊木准教授は遺跡のこととなると、とたんに言葉が踊り出します。

東京大学大学院人文社会系研究所付属北海文化研究
常呂実習施設 准教授 熊木俊朗さん
オホーツク人はなぜやって来たのか? そして500年ののちなぜ消えたのか? それらの背景には何があったのか? 仮説を立てながら遺跡を発掘し、地道に検証してゆく。仮説が当たれば高揚するし、仮説がくつがえされても修正をしながら研究を進めてゆく。このプロセスのすべてが面白いのだと、熊木准教授は言います。
「学生時代、実習で初めて常呂に来た時、海がきれいな所だなって思いました。家族とともに暮らす今も同じ。夏はワッカの先で静かな海を見るのが好きです」。考古学研究と教育活動で生きる、東京出身の常呂住民は、オホーツクの海のような穏やかな表情で、目には情熱を映していました。


①「東京大学常呂資料陳列館」に保存されているオホーツク文化の土器類。
② オホーツク人と大陸との交易を物語る、青銅の装飾品や鉄の武器も出土しています。
③ 約4キロに渡る「常呂竪穴住居群」は世界でも大きな遺跡。この範囲に約2,500の竪穴住居跡があり、このエリアは国指定の史跡として保存されています。夏は復元された竪穴住居に入ることも可能です。
④ 白樺林の中に建つ「東京大学常呂資料陳列館」 北見市常呂町字栄浦 開館時間:9時〜17時 休:火曜・祝日 入館:無料